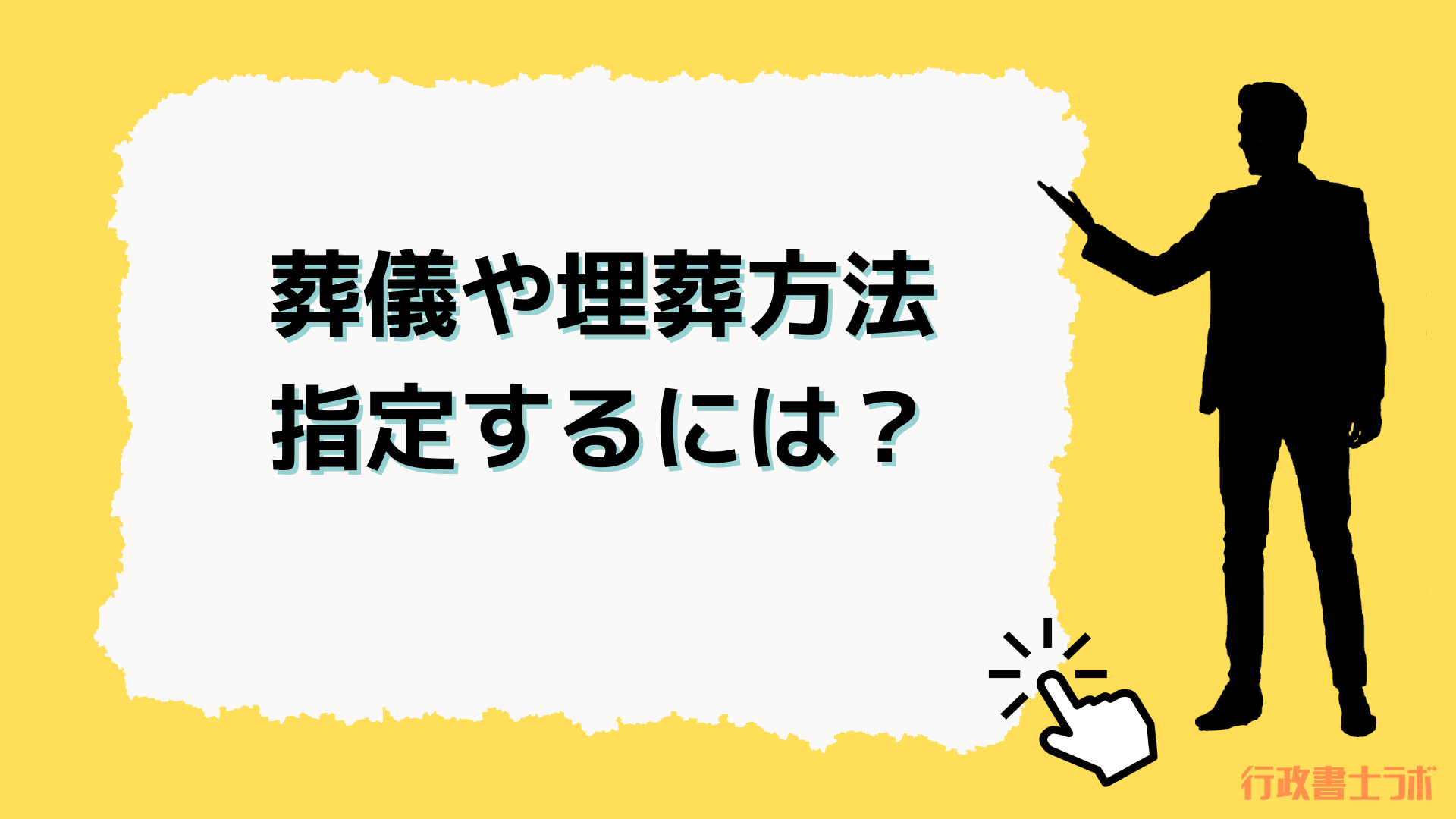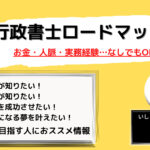葬儀、埋葬方法(以下、葬儀方法)やその後お墓の管理などご自身の意思で指定しておきたいと考える人がいます。
その理由として、死後、遺族の負担を少しでも減らしてあげたいという想いからではないでしょうか。
自分自身が、母の葬儀やその後のお墓管理(お参り)で苦労したことがきっかけです。
できれば、生前に葬儀方法を決めておくことで、例えば指定した葬儀屋に任せ、お墓の管理(永代供養)をしてくるお寺を探しておけば遺族はありがたいと思うはずですよね。
このような思いから、葬儀方法など事前に指定しておきたいと考えるのです。
指定方法として、まず遺言書を考えるはずです。しかし、遺言書での指定(葬儀方法など)はできないので注意が必要です。
今回、なぜ遺言書できないのかを含め、最善の方法をご紹介します。
遺言書は、葬儀や埋葬方法を指定したところで法的効力がないから意味がない
なぜ?葬儀方法の指定が遺言書できないかについて解説します。
実際に遺言書で指定ができないわけではありません。遺言書には、法的効力がある内容と法的効力がない内容の両方が書けます。
そして、葬儀方法やお墓管理などの指定は、法的効力がない内容になるのです。法的効力がないということは拘束力がありません。
ですので、残れた遺族は遺言書に書いてある葬儀方法などを実行する義務はないのです。
このような内容を書いたとしても、あくまでも遺族へ向けたご自身の希望になってしまうだけです。
遺言書で葬儀方法の指定は意味がない。発見される前に葬儀は終わっている
そんな法的効力がない内容の遺言書でも・・・遺言者の想いを汲みとった遺族が内容通りに実行してくれるかもしれませんよね。
それでも、遺言書で葬儀方法を指定しておくのは辞めておくのがいいでしょう。
なぜなら、遺族が遺言書の内容を確認する前に葬儀や埋葬が終わってしまうからです。
以下で、死亡してから遺言書の内容確認までの流れを順に紹介します。
- 死亡(死亡届)
- 葬儀・埋葬(葬儀費用清算など)
- 遺産整理(遺言書発見)
- 相続手続き(遺言書の内容確認)
このように、2の葬儀・埋葬がすべて終わってから遺産整理中に遺言書が発見させることが多いです。
その後、4の相続手続きの時に初めて遺言書の内容を確認することになるのです。
では、葬儀を行う前に遺言書を確認すれば問題ないのでは?と思うかも知れませんが、内容を他人に知られたくない遺言者もいますよね。ましてや、ご自身で書く自筆証書遺言の場合、すぐに遺言書の内容を確認することはできません。
なぜなら、検認手続きというものがあるからです。
検認手続きは、裁判所側で遺言書の開封し相続人全員で確認する作業です。
このことから、時間の誤差による問題が発生するので、葬儀方法の指定を遺言書でするのは辞めた方がいいです。
遺言書で葬儀方法を書くときの注意点
それでも、遺言書で葬儀方法などを指定したいと考える人もいるでしょう。
その場合は、遺言者は公正証書遺言で作成することと遺族へ事前に了承を得ることが大切です。
公正証書遺言なら検認手続きがありませんので、すぐに内容を把握できスムーズに実行することが可能になるからです。
また、ご自身が希望する葬儀方法はかえって遺族を困惑させる場合があります。
例えば、遺言書で「葬儀や埋葬は行わず、遺骨は海を撒いてほしい」と書かれたとします。
しかし、その内容を読んだ遺族全員が了承するわけではありません。中には、「葬儀や埋葬はやるべき」と考えている人もいるかもしれませんよね。
そうなってしまえば、遺言者の想いを汲み取りたい遺族とそれとは逆の考えの遺族で揉める原因になってしまいます。
このようなことから、遺言書で葬儀方法を指定する場合、事前にその旨を説明し遺族から了承を得ておくようにするのが望ましいでしょう。
義務が発生する死後事務委任契約がいい
遺言書で、指定するよりも確実な方法があります。
それは生前の死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、死後、葬儀やお墓関係などさまざまな手続きが発生しますので、その手続きを委任し、生前に受任した者が委任契約の内容に沿って手続きをすることです。
例えば、委任する内容は火葬、納骨、埋葬に関する事務や永代供養に関する事務など内容は多義になります。
死後事務委任契約は、委任者と受任者との双方契約になるので内容を実行する義務が発生します。
ですので、このような契約することで、よりご自身の希望に沿った終活が可能になります。
簡易なエンディングノートも活用する
また、最近ではエンディングノートを作成しておくのもいいでしょう。
死後事務委任契約ほど厳格な手続きはするのはちょっと…思う人は、エンディングノート作成しご自身の希望を指定しておくのもいいです。
エンディングノートに法的効力はありませんが、葬儀方法含め、財産の処分方法や遺族への想いなど、ご自身の希望する終活ができるように書くノートです。
その作ったエンディングノートを見た遺族は、作成者の想いを汲みとり手続きを進めてくれるようになるのです。
まとめ
ここまでで葬儀や埋葬方法の指定について解説してきました。
遺言書での指定はおすすめできないことが分かったと思います。遺言書の有無は、葬儀や埋葬が終わってから分かるものです。
せっかく指定したにも関わらず、これでは希望した意味が無くなってしまいますよね。ましてや、残された遺族も後味の悪いものになってしまうでしょう。
そうならないために、確実な方法を取っておくことがおすすめです。
それは、検認不要な公正証書遺言で作成しておくことや事前に遺族の了承を得ておくこと。
また、より確実な死後の事務委任契約やエンディングノートを作っておくのも、ご自身の希望を叶えるために有効です。
今回はこれで以上です。
- 人に役立つ仕事がしたい!
- 脱サラして独立開業したい!
- 手に職を付けたい!
- 会社の給料に不安を感じた!
- フリーターから脱却したい!
行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
⇩⇩